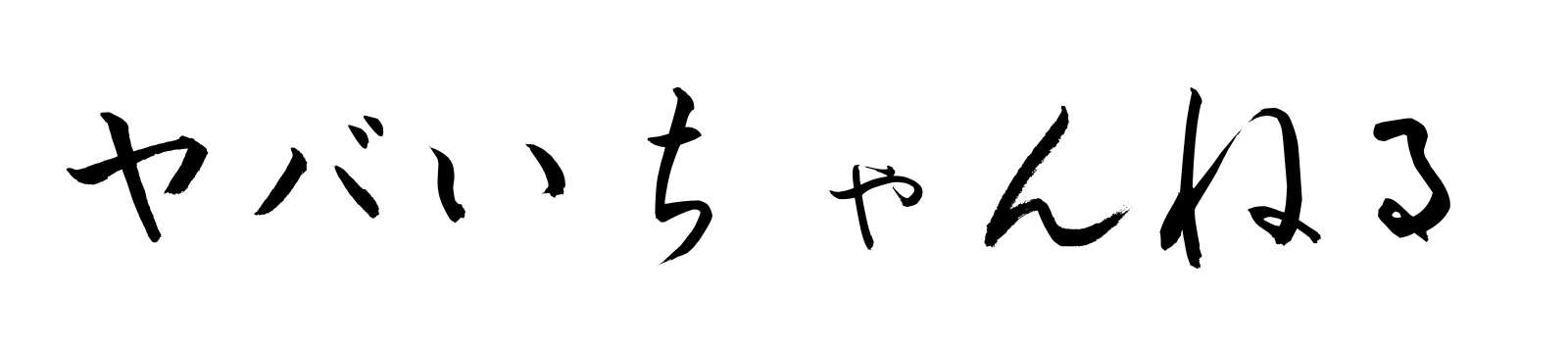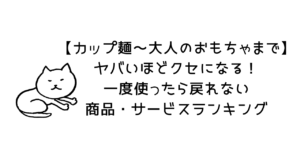「たかの友梨ビューティクリニック」と言えば、日本を代表する高級エステブランドの一つ。
その名前を聞いただけで、「セレブ」「一流」「効果がありそう」といったイメージを持つ人も少なくないだろう。
創業者である高野友梨氏は、テレビ出演や広告などを通じて「美容界のカリスマ」としての地位を確立し、長年にわたり“美の帝国”を築き上げてきた。
しかし、近年ネット上では「たかの友梨がやばい」「信じられない接客をされた」「スタッフがブラックすぎる」といったネガティブな投稿が増加中。これまでの輝かしいイメージとは裏腹に、その裏側には驚きのトラブルや批判が渦巻いているのだ。
本記事では、そんな「たかの友梨が現在やばい」と言われる背景を、過去の労務問題から現在の顧客評価、企業体質に至るまで、5つの切り口から徹底的に検証する。
過去の栄光と現在の評判のギャップに、あなたも驚くかもしれない。
【関連記事】こちらもおすすめ!
1. パワハラ音声の流出と労務問題がやばい
たかの友梨の「やばさ」が一気に世間に知られたのは、ある労務トラブルをきっかけとしたパワハラ音声の流出事件だ。
2014年、宮城県のたかの友梨仙台店に勤務していた女性従業員が労働組合に加入したことをきっかけに、経営陣からの圧力や嫌がらせを受けたと訴えた。
とくに衝撃的だったのは、創業者・高野友梨氏自身がこの従業員と直接面談した際の音声が録音され、ネット上で公開されたこと。
この音声の中で高野氏は、「組合に入るなんて裏切り」「私は社員にそこまでしてやらなきゃいけないの?」と発言しており、これが「パワハラではないか」と炎上。テレビでも報道され、企業イメージは一気に悪化した。
さらに、他の元従業員からも「長時間労働」「妊娠中にもかかわらず深夜まで働かされた」「辞めたいと言ったら無視された」といった告発が相次いだ。
企業体質そのものがブラックではないかという疑念が広まり、法的にも訴訟へと発展したケースもある。
こうした事件は10年近く前の出来事とはいえ、SNS上では今もなお語り継がれており、「たかの友梨=パワハラ企業」という印象が根強く残っている。
2. 高額勧誘・強引な接客がやばい
たかの友梨を利用した顧客の中には、「説明もそこそこに高額なコースを勧められた」「断ると態度が急変した」と語る人も多い。
口コミサイトやレビュー投稿には、スタッフによる強引な営業トーク、初回体験後の“囲い込み”のような流れに違和感を覚えたという声が多数見受けられる。
特に問題視されているのが、「お得な回数券」や「今だけの特別価格」といったセールストークで数十万円単位の契約を迫るケースだ。「少し考えたい」と伝えると、「今決めないとこの金額ではできませんよ」とプレッシャーをかけてくるパターンも報告されている。
また、解約・返金対応が不透明という口コミも多く、「クーリングオフ期間を過ぎたら一切返金不可」「電話がつながらない」「対応が冷たすぎる」といったトラブルが絶えない。
こうした経験から「たかの友梨はやばい」「もう二度と行かない」と感じた人が少なくないようだ。
長年エステ業界で君臨してきたたかの友梨だが、消費者保護の観点から見ると、その営業手法や接客スタイルは時代遅れと言わざるを得ない。
【関連記事】こちらもおすすめ!
3. 効果が出ない?顧客満足度の低下がやばい
エステに通う目的の多くは「痩せたい」「きれいになりたい」という明確な成果への期待だ。
しかし、たかの友梨に通った顧客の一部からは「何十万円もかけたのに全然効果が出ない」「逆に肌が荒れた」といった厳しい声が上がっている。
とくに痩身コースに関しては、「機械は最新っぽいけど、実際は寝てるだけ」「食事指導も雑で、効果が続かない」といった口コミが複数存在。
中には、「ビフォーアフター写真の加工が過剰では?」と疑問を投げかける声もある。
もちろん効果の感じ方は個人差があるが、高額な費用を払った顧客の期待値が高いだけに、それに見合った満足感が得られなかった場合の不満は大きい。
さらに、施術者の技術にばらつきがあるという指摘もあり、店舗によって評価が大きく分かれるのも懸念点だ。
“高級エステ”を謳いながら、その実態が「金額に見合わないサービス」であれば、リピーターは離れ、ブランド価値も徐々に低下していく。
これが現在の“やばい状態”に拍車をかけているのは間違いない。
【関連記事】こちらもおすすめ!
4. SNS・ネット上の評判がやばい
現代においてブランドの命運を左右するのが、SNSを中心としたネット上の評判だ。
たかの友梨も例外ではなく、X(旧Twitter)や口コミサイトでは厳しい意見が目立つようになってきた。
「行ったら予想以上に勧誘がしつこかった」「雰囲気が冷たい」「完全にお金持ち向け、庶民にはきつい」という感想がリアルタイムで拡散されており、Googleの口コミでも星1〜2の低評価レビューが少なくない。
一部では、体験予約をしただけで「その後しつこく電話がかかってきた」「キャンセルを断ってもしつこく再予約を迫られた」といった個人情報の扱いに不安を覚えるような報告も。
こうした声がSNSで広がると、未利用者も「ここってやばいんじゃない?」とイメージを悪化させる結果に。
情報拡散が速い今の時代、一度炎上したら鎮火は難しい。
たかの友梨は、口コミやSNS対策の遅れが、ブランド力低下という“やばい現実”を招いていると言える。
【関連記事】こちらもおすすめ!
5. 組織体質・時代とのズレがやばい
最後に注目すべきは、たかの友梨という企業そのものの体質だ。
トップダウン型のカリスマ経営は、かつては成功モデルとされたが、今では“危うい企業運営”と捉えられることも多い。
創業者・高野友梨氏は広告塔として大きな影響力を持っていたが、過去の労務トラブル以降は表舞台に出ることも減り、企業の意思決定プロセスやガバナンス体制にも不透明感が残る。
社員教育やコンプライアンス意識の低さを指摘する声もあり、「老舗なのに中身が昭和のまま」という批判も聞こえる。
さらに、エステ業界そのものが今、大きな転換期を迎えている。
ホームケア機器の普及や美容医療の進化により、高額エステの必要性が薄れてきているのだ。
その中で、価格・対応・技術すべてにおいて旧態依然としたままでは、時代の波に取り残されるのも時間の問題だ。
【関連記事】こちらもおすすめ!
まとめ
たかの友梨が「やばい」と言われる背景には、単なる一過性のトラブルではなく、長年積み上げられた“ブランドと現実のズレ”があると言える。
かつては「美と成功の象徴」として圧倒的な影響力を持っていたが、現代の顧客はよりシビアで、サービスの質や企業姿勢を敏感に見極めている。
過去のパワハラ問題、高額勧誘の手法、効果の不透明さ、そしてSNSでの評判の悪化——これらが複合的に絡み合い、たかの友梨は今まさに“ブランド崩壊の危機”に立たされている。
顧客が求めるのは、豪華な内装でも、過去のネームバリューでもなく、「信頼」と「成果」であることを、このブランドが再認識できるかが、今後の生き残りの鍵だ。
「やばい」と言われている今こそ、たかの友梨がどう変わるか。その一挙手一投足に、美容業界全体の未来がかかっているのかもしれない。
【関連記事】こちらもおすすめ!